【PACファンレポート⑫ 第96回定期演奏会】
五月晴れの5月27日、兵庫芸術文化センター管弦楽団(PAC)の第96回定期演奏会は、定期での指揮は8回目、2014年3~6月にはPACとともに「シューマン&ブラームス・プロジェクト」にも取り組んだ下野竜也が登場。対照的な2曲を見事に演奏し、鮮やかな印象を残した。
1曲目はホアキン・ロドリーゴ(1901-1999)の「アランフェス協奏曲」。18世紀スペインの宮廷の情景を追想して作曲された名曲だが、作曲家が3歳の時に視力を失っていたことを、今回のプログラムを読むまで私は知らなかった。ロドリーゴの想像の中に立ち現れた幻が、彼に不朽の名曲を書かせたのだろうか。第2楽章の哀愁を帯びた美しいメロディーはあまりにも有名で、クラシックだけでなくジャズやフュージョン音楽のアーティストたちも数多くカバーしている。
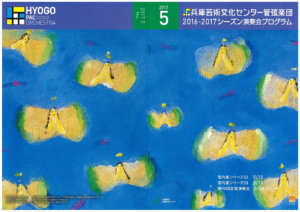
今回はソリストに日本を代表するハープ奏者・吉野直子を迎えてのハープ協奏曲版。演奏前に舞台中央に黄金色に輝くハープが置かれ、まず聴衆の目を釘付けにした。通常の演奏会ではハープは舞台左側に置かれ、聴衆は楽器の側面を見ている。ソリストが聴衆と相対して座る形になると、台座部分にどっしりした厚みがある楽器の存在感が際立つ。
その楽器に負けない、光をまとったきらびやかな衣装で登場した吉野は、滑らかに左右の指を動かしながら舞うように演奏。天上の音楽のように上品かつ華やかな音がホールに満ちた。その音のふくらみに魅了された二十数分間は、あっという間に感じられた。
実際にはハープの演奏は、47本の弦と7本のペダルを、両手両足を使いながら演奏し、かなりハードなのだそうだが、それを感じさせない優雅な演奏スタイルはさすが(水の上を滑るように泳ぐ白鳥の足が、忙しく動いているのときっと同じなのね)。
吉野のアンコール曲は、ルニエ「黙想」。PACメンバーたちも、美しい未知の曲に耳を澄ましていた。
繊細な美しさをたたえた協奏曲から一転、オーケストラの演奏はアントン・ブルックナー(1824-1896)の「交響曲第6番」。過去のPAC定演で、下野はブルックナーの交響曲を4番、7番、8番、9番と演奏してきた。20代後半だった1997~99年に朝比奈隆音楽監督率いる大阪フィルハーモニー交響楽団で指揮研究員を務めた下野の脳裏には、師であった朝比奈氏が得意としたブルックナーは、青春の情熱や胸の高鳴りと分かちがたく結びついているのかもしれないなと、ふと思う。
コンサートマスター四方恭子のほかにヴァイオリン26人(OB・OG6人を含む)、ヴィオラ10人(OG1人を含む)、チェロ8人、コントラバス6人という大編成の弦。金管もホルン5人、トランペット4人、トロンボーン2人にチューバ。これにフルート、オーボエ、クラリネット、バスーンの木管楽器が各2人。ティンパニを加えて総勢72人が、55分にも及ぶ重厚長大な曲を、集中力を切らさないで、音を合わせて演奏する。それは本当に、奇跡のようなことではないだろうか。演奏会が終われば、同じメンバーで同じ曲を演奏することは、おそらく二度とない。演奏会とは、そんな奇跡に遭遇できる空間なのだ。
リズミカルに展開する第1楽章。大河の流れのようにゆったりと回遊しながら、伸びやかに美しいメロディーが立ち上がる第2楽章。再びリズミカルに走り出す第3楽章。ひそやかな音の戯れに心地よく身を委ねていると、徐々に曲想は壮大な輪郭を描き始める。
第4楽章。全楽器が軽快に大音量で鳴り響き始める。大きな音の余韻の後に、静かな演奏パートが揺れながら高まり、再び突然の大音量。雷鳴のようなティンパニが容赦なく空間を切り裂く。全員がこれでもかと音を鳴らす、まさに“爆発”が繰り返し訪れる。その激しさは、やはりPACの若さに似つかわしく思える。
ゲスト・トップ・プレイヤーとして、東京フィルハーモニー交響楽団からヴァイオリンの戸上眞理(第2ヴァイオリン首席)とコントラバスの黒木岩寿(首席)、関西フィルハーモニー管弦楽団からヴィオラの中島悦子(同楽団特別契約首席、神戸室内合奏団)とチェロの向井航(同楽団特別契約首席)、ホルンの阿部雅人(元新日本フィルハーモニー交響楽団奏者、沖縄県立芸術大学准教授)、トランペットの佐藤友紀(東京交響楽団首席)が参加。スペシャル・プレイヤーにヴァイオリンの田中晶子(シベリウス国際、ミュンヘン国際、ヴィエニャフスキコンクール上位入賞、桐朋学園大学講師)、水島愛子(元バイエルン放送交響楽団奏者、PACミュージック・アドバイザー)が名を連ねた。
(大田季子)

